
学校時代 – 高校生(セイ)ブン・大学生(セイ)ブンだった頃の僕.
「学校時代」というタイトルで、今回の記事を始めて置きながら、書き始めてすぐさま、こんな事を書くのも、おかしな話だが、まともな意味での、学校時代などというものが、僕自身に、あった訳ではない。そんなものは、なかった。
僕の学校生活が、仮にも、普通っぽかったのは、小学生時代の生活と、中学校時代の生活だけだ。あとは、もう、メチャクチャ。思い出したくもない、おぞましい記憶しかないから、今の今まで、心にフタをして、なるべく、思い出さない様にしていた位なのだ。
でも、今では、その、「メチャクチャな時代」に、感謝している。その事も、記事の後半で、書く。
本題に入る前に、その、学校時代とやらに、至るまでの、僕の、個人史、その流れを、説明しよう。
僕の生まれ育った家庭は、エリート色が、極度に、濃かった。人間の価値は、頭の出来具合いで決まるという、強い信念を、僕の両親は、持っていた。けれども、その家庭に生まれた僕には、エリート傾向は、なかった。文学的・音楽的な感受性は、人一倍、豊かだったが、そんなものは、両親にとっては、ものの数ではなかった。
そんな環境の中で、幼くして、すでに、「ダメな奴」と、レッテルを貼られた。それは、ごく、当たり前で、自然な事だったろうと思う。単一の価値観がすべてである空気の中では、その価値観にそぐわない人間は、その価値観の外で、他に、何があろうと、みな、ダメ人間に決まっている。もしも、その立場が逆であったなら、親である僕が、子供である「セイブン君」を、親が僕を見ていた通りに、見ていたに違いないのだ。
その結果、僕は、幼い頃から、できる事は、一切、認められず、できない事だけを、ことさらに、あげつらわれる様になった。「ダメ人間だ」と決められたのだから、それは、当然の事だった。ダメ人間は、ダメでなければいけない。いいところ、長所などがあっては、ダメ人間ではなくなってしまう。だから、その様になった。誰が悪いという事も、誰が間違っているという事もなかった。僕が、誰かを、ダメ人間だと決め、その判断の正当性を、感じ続けたかったら、その判断が、誤っていたと、認めたくなかったら、僕自身、その誰かに、同じ事をする。
で、話を、ギュッと短くすると、そうやって、否定され、それを受けて、自分でも、自分自身を否定する事を、毎日、毎週、毎月、毎年、繰り返している内に、幼い頃から、長年、積み重ねられて来た自己否定感情で、心が、いっぱいに満ちてしまって、僕は、無気力感で、何も出来なくなってしまったのだ。当たり前と言えば、余りにも、当たり前過ぎる事だった。どうせ、何をやっても、ダメだ….そんな気持ちで、いっぱいになっているのに、何をやる気にも、なる訳がない。そうなった時、僕は、高校2年生だった。こうして、今、当時の事を、思い出しながら、書いていると、その頃の気持ちが、よみがえって来る。空虚感。無意味感。無力感。無気力感。無能感。自己愚劣感。自己醜悪感。生きている手ごたえが、感じられない。自分など、いようが、いまいが、世界は、何も変わらないし、気にもしない。自分が、自分である事は、醜くて、愚劣で、それ自体がネガティヴで、そこには意味もなく、尊厳だって、もちろん、ない。僕は、自分自身の存在を、バケモノか、何かの様にしか、感じられなかった。
高校2年生だった僕は、夜も、眠れなくなり、その結果、学校にも、まともに行けなくなった。意志の問題では、全く、なかった。夜、眠ろうとしても、眠れず、だから、朝になっても、眠くて、眠くて、到底、学校になど、行けず、眠ってしまう。がんばりなど、利く状態では、もはや、なかった。そんな調子で、高校生としての生活を続けた。午前中の授業などは、全然、出られず、遅い時間の授業にだけ、出た。成績の方は、どうなっていたのか、まるで、わからない。留年になる事もなく、退学になる事もなく、無事に卒業できたのが、不思議だった。これは、その高校が、英語の能力を重視する学校だったからかも知れない。僕は、イギリスで、2年近く生活したのちに、日本に帰って来た、いわゆる、帰国子女だったから、英語の能力は、高校の英語教師達よりも、上だった。少なくとも、その高校では、明らかに、そうである様だった。
高校を卒業しても、僕の、精神的なコンディションは、何も、変わらなかった。両親には、そんな僕を気遣う様子は全くなく、それどころか、それまで以上に、否定され、メチャクチャな事を言われ、デタラメな扱いをされて、僕の精神状態は、快方に向かうどころか、ますます、悪くなっていった。恐ろしい事には、そんな状態で、大学に入学させられ、通う事を強いられた。でも、こうして、当時の事を思い出しながら、書いていて、今さらになって、ふと、気づくのだが、無理強いされてでも、大学の入学試験を受けて、合格したのだから、少なくとも、それに見合う能力は、あったのだ。
だが、すでに前述した様に、「できる事は一切認めず、できない事だけを見て、あげつらう」というのが、両親の、僕に対する、幼い頃からの、一貫した、徹底した態度だったので、その時も、能力を認められる事は、なかった。そして、死ぬほどつらく、苦しい、大学時代が、始まった。相変わらず、夜は、眠れず、だから、朝になっても、眠くて、一日を始める事など、到底、出来ず、眠り込んでしまう。眠いままで、何とか、持ちこたえて、目を覚まし続け、大学に向かう事もあったが、そもそもからして、やる気が起きない事を、無気力な自分に無理強いして、やろうとしている上に、寝不足で、眠くて仕方がないのでは、学生として、まともに勉学など、出来る訳もなかった。しかも、家から大学までは、2時間もあった。往復で2時間ではない。片道で2時間、往復で4時間だった。延々と、3つの電車線を乗り継いで、大学に通う事自体が、徐々に、苦痛でたまらなくなった。朝から眠って、午後に起きてでも、とにかく行けば、間に合って出られる、遅い時間の授業にさえも、行かず、出席しないで終わる一日も、増えていった。そんな生活を、毎日、毎週、毎月、毎年続けて、結局、数年後に、退学せざるを得なくて、退学した。もともと、両親のエゴを満たす為だけにあった、大学生活だったから、その結果自体には、僕は、何の感傷もなかった。むしろ、今になって、考えて見れば、卒業など出来なくて、良かった。心底から、今、そう、思う。卒業できなかった事に、感謝さえ、している。
あの、痛みと苦悩で満ちた、大学時代が、一見、年月を無駄に費やしただけであったかの様な、大学時代が、それまでは、ただの「セイブン」(音読みで)だった僕を、「ココロのセイブン」に、変えた。僕は、今、カリフォルニア全域に至る、UCという大病院の、サンディエゴの精神科練(サイキ・ユニット)で、心病んだ人達、心傷ついた人達、心の機能を失った人達を助ける仕事をして、充実した日々を過ごしている。
…..と、それだけで、話が終われば、めでたし、めでたし….だったのだが、実は、話の続きがある。
その、大学生活とも呼べない、僕の大学生活、大学生時代の年月は、深い、深い、心の傷となって、それから、さらに、数十年間も、僕に、つきまとい、僕を、苦しめ続けた。忘れようとしても、忘れられるものではなかった。夢の中で、僕は、たびたび、その頃の自分に戻った。そして、現実の生活では、すでに終わっていた、大学生活の苦痛、屈辱、無力感を、繰り返し、繰り返し、味わわされた。大学生活が終わってから、何十年も経って、もはや、日本にさえいず、遠いアメリカで生活していても、「そんな事は、知った事ではない」と、言わんばかりに、平然と、その悪夢は現れて、僕の夜を、そして、それに続く、朝の目覚めを、みじめな色に染めた。悪夢の様だ….という表現があるが、それは、「…..の様だ」ではなくて、文字通り、言葉通りの、悪夢・それ自体だった。
両親と同居していた家自体は、じきに、あとにする事になった。その、環境そのものが、どうやら、問題らしい…..と、やっと、気づいたからだ。このままでは、僕は、廃人にさえ、されかねない….そんな、危機感さえ覚えて、僕は、その家を出て、ひとりで、アパート暮らしを始めた。幸い、その、僕の判断が、正しかった様で、僕は、その時点をスタートに、徐々に、心を取り戻していったのだが、前述の、字義通りの、悪夢も、その時から、始まった。
最後に、その悪夢を見たのは、いつだったろうか。去年だったか、それとも、おととしだったか。
前述の通り、ひとり暮らしを始めて、徐々に、心を取り戻していった僕は、これも、前述の通り、ついには、アメリカで、現地で出会った女性との結婚生活を送りながら、病院の精神科練で働いて、生計を立てるまでになったのだが、もうひとつおまけに、前述の通り、悪夢は、アメリカに移ってまでも、僕につきまとい、夜に現れては、僕を、悩ませ続けた。
けれども、たった今、思い出したのだが、その、最後の夢の中で、僕は、その状況を、変える決心をした・出来たのだったと思う。
それ以来、その悪夢は見ていない。



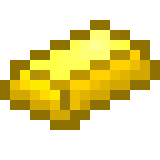
コメントを残す